私が日本で運転免許を取得した方法
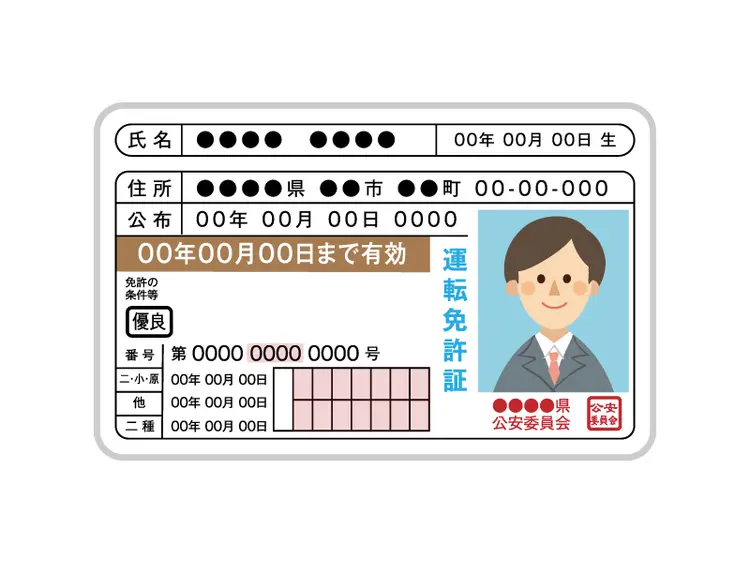
今日、ついに日本で運転免許を取得しました、皆さん!それほど難しくはなかったけど、注意すべき点がいくつかあります。この記事で皆さんにシェアします。参考にして、運転の勉強をする際に気をつけてくださいね。私が学んだプロセスに沿って書いていきます。
ステップ 1:運転免許が必要か考える
私はベトナムで運転免許を持っていなかったし、車を運転したこともありませんでした。まあ、大学時代に運転したことはあるけど、それは別の種類の車両でした: 現在、日本では IT の仕事をしており、在宅勤務なので通勤のために運転する必要はありません。でも、遊びに行くためですよ、皆さん!私が運転免許を取ろうと決めた主な理由は、旅行して日本各地を探索するためです。だから、あれこれ悩まずに、努力して学ぶことにしました。
現在、日本では IT の仕事をしており、在宅勤務なので通勤のために運転する必要はありません。でも、遊びに行くためですよ、皆さん!私が運転免許を取ろうと決めた主な理由は、旅行して日本各地を探索するためです。だから、あれこれ悩まずに、努力して学ぶことにしました。
ステップ 2:日本での免許取得について調べる
YouTube やいくつかのブログで、日本での運転免許の取得方法を調べました。調べた情報には、スクールの選び方、費用、試験、車の価格、レンタカーの費用などが含まれます。難しそうでもなく、費用もそれほど高くなかったので、さっそく始めることにしました。
ステップ 3:運転学校を見つける
いろいろな種類があることがわかりました。日本語で教える学校、ベトナム語で教える学校、合宿形式の学校、自由な時間に学べる学校、公安委員会指定の学校、指定されていない学校など。ざっくりこんな感じです:
- 形式:
- 合宿形式:
- スクールで約 2 週間集中的に学びます。仕事の予定を調整して 2 週間休みを取り、免許取得に専念する必要があります。
- 通学形式:
- 空いた時間に学習をスケジュールします。例えば、夕方、土日、祝日など。この形式は少し時間がかかり、通常 3 ~ 4 か月。私の場合は個人的な理由で 6 か月かかりました。
- 合宿形式:
- 公安委員会指定:
- 指定校:
- 実技試験をスクールで、学科試験を免許試験場で受けます。
- 費用は高め(約 30 万円)ですが、スクールの指導員が採点するので実技試験に合格しやすいです。
- 非指定校:
- 実技試験と学科試験の両方を警察署または免許試験場で受けます。
- 費用は安め(ベトナム語で教える学校では 17 万円のところもありました)が、警察官が採点するので実技試験に合格するのが難しいです(先輩の経験談では、何度も落ちて諦め、指定校に切り替えた人もいました)。
- 指定校:
私の場合、先輩やインターネットで調べた結果、家から近い公安委員会指定の学校で通学形式を選びました。私が通った学校はこちら:Nagareyama Driving School
レビューを見ると、評価はあまり高くなく 2.7/5★。ちょっと不安でしたが、コメントを見ると主に指導員への不満が多いようでした。しかし、5 つ星のレビューを見ると指導員を選べることがわかったので、大丈夫だろうと思い、決めました。
ステップ 4:学校に登録に行く
登録に行く前に、学校のウェブサイトで必要な持ち物を確認しました:
- 住民票:マイナンバーカードがあればコンビニで印刷できます。
- 身分証明書:マイナンバーカード、パスポート、または健康保険証。
- 印鑑。
- メガネ(視力・聴力検査用)。
- お金(クレジットカードまたは現金。ウェブサイトでコースの料金を確認)。
- IC カード(実技の際に車にチェックインするために使用)。
- 写真 4 枚(学校で撮影できるので、私はそこで撮りました)。
- 申込書(学校で記入)。
書類を揃えて学校に行き、登録しました。手続きは簡単で、スタッフが案内してくれてコースを説明してくれました。自分に合ったコースを選び、質問があれば登録前に聞きました。登録して支払いを済ませると、視力・聴力検査(普通の視力検査で、遠近の視力や色の識別能力をチェック)を受けました。検査に合格すると、開講日を予約して帰宅しました。
ステップ 5:開講式
開講日には、学校の詳細な紹介を聞きました。必要な教科書が配られ、その後、適性検査を受けました:
- テストは面白く、時間が長く、初めて見るものでした。
- 問題用紙と回答用紙が配られ、一定時間内にできるだけ多く答える必要がありました。
- 問題は幾何学に関するもので、異なる図形を見つけたり、似ている図形を選んだり、数を数えたりするものでした。
- テスト後、結果が返され、「安全」「集中力散漫」「反応が遅い」などのグループに分類されました。これは自分の能力を知るためのものでした。手続きが終わったら帰宅しました。
ステップ 6:授業を受ける
授業は学科と実技の 2 種類:
- 学科授業:
- 事前予約は不要。手続き時に時間割表をもらいました:

- 自分の都合に合わせてクラスを選び、順番に関係なく全授業を受ければ OK。
- 事前予約は不要。手続き時に時間割表をもらいました:
- 実技授業:
- 事前に予約が必要。私の学校ではアプリで予約し、時間になったら授業を受けました。
学習と試験のプロセスは長かったので、以下にまとめます:
- フェーズ 1:仮免許(指導員同伴で公道を運転できる免許)取得:
- 学科 13 講義と実技 12 回(21 項目)を修了。
- 学科が終わったら学科評価試験を受け、合格すれば実技評価試験へ。失敗したら学科を復習。私の学校ではMusasiアプリで試験対策。
- 学科評価試験に合格したら実技評価試験を受け、合格すれば本試験へ。失敗したら実技を復習して再受験。
- 実技評価試験に合格したら公式実技試験。
- 公式実技試験に合格したら視力・聴力検査。
- 視力・聴力検査に合格したら仮免許試験(学科、50 問)。
- 仮免許試験に合格したら仮免許が発行(学校が保管)し、フェーズ 2 へ。
- フェーズ 2:本免許(正式な運転免許)取得:
- 学科 16 講義と実技 19 回(16 項目)を修了。
- 学科が終わったら学科評価試験を受け、合格すれば実技評価試験へ。失敗したら学科を復習。Musasiで試験対策。
- 学科評価試験に合格したら実技評価試験を受け、合格すれば公式実技試験へ。失敗したら実技を復習して再受験。
- 実技評価試験に合格したら公式実技試験。
- 公式実技試験に合格したら卒業式。
- 卒業式で、免許試験場での本試験の案内を受け、卒業証明書(1 年間有効)を受け取る。
ステップ 7:本試験を受ける
運転学校で卒業証明書を受け取ったら、交付された書類を持って免許試験場で本試験を受け、免許を取得します。注意点は以下の通り:
- 住んでいる都道府県の免許試験場で受験。
- 学科試験は 95 問、50 分。
- 事前にしっかり勉強が必要。授業でカバーされない問題もあるので、複数のウェブサイトで練習することをお勧めします。私が使ったサイト:
- 95 点以上を安定して取れるようになってから受験しないと、時間とお金の無駄になります。私の試験場では再受験に 1,750 円かかり、平日に休みを取る必要がありました。自信がついたら受験。合格後、もう一度視力・聴力検査を受けます。小さな注意点:近視が軽度または不要なら、視力検査はメガネなしで受けましょう。メガネをかけて検査すると、免許に「メガネ着用条件」が付き、運転時にメガネをかけないと減点や罰金になります。この条件の解除は簡単で無料ですが、追加で手続きに 1 日かかります。免許を取得したら、車を購入またはレンタルしてドライブ開始!皆さんの成功を祈ります!